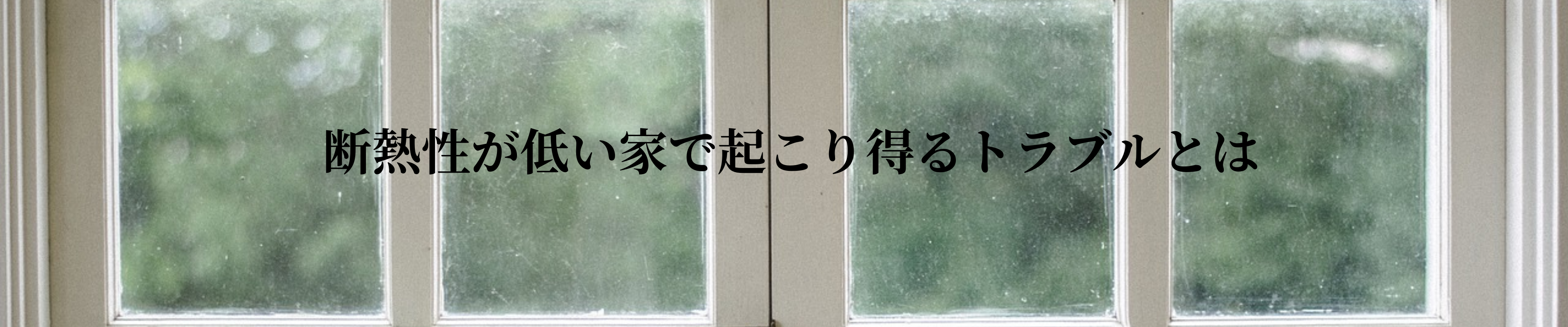
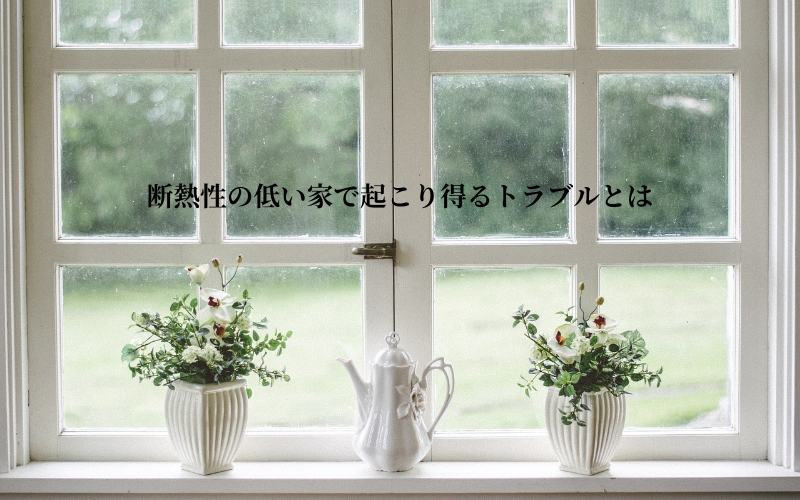
2025/1/14 COLUMN
断熱性が低い家で起こり得るトラブルとは
マイホームを建てる際には、デザインや設備など、こだわりたい点がたくさんあると思います。
しかし、家の断熱性能は、快適な暮らしを実現するために欠かせない重要な要素です。
断熱性能の低い家で起こり得るトラブル、断熱性能の基本を分かりやすくお伝えします。

断熱性能とは、外部の熱を遮断し、内部の温度を一定に保つための性能を指します。特に建築や住宅設計、設備機器などで重要な指標となります。この性能が高いと、外部の暑さや寒さの影響を受けにくくなり、室内の快適性が向上します。また、冷暖房に使うエネルギーが減少するため、省エネルギーや環境負荷の低減にも寄与します。
断熱性能を評価する上で重要な要素には以下があります。
材料が熱を伝える速さを示し、数値が小さいほど断熱性能が高いです。
壁や窓などの建築部位を通過する熱量を示し、数値が低いほど、熱の損失が少なく断熱性能が高いといえます。(ただし地域により異なる)
建物の壁や天井、床に使われる材料です。例えば、グラスウール、発泡スチロール、ポリウレタンフォームなどが代表的です。
建物内部と外部の空気の流れを防ぐ性能で、気密性が高いと、断熱性能も効果的に発揮されます。
断熱性能が高いことで、快適性の向上・エネルギー効率の向上・結露の防止・環境負荷の低減などの点があげられます。
住宅の断熱性能を評価するための基準やラベルとして、・HEAT20(G1・G2基準)・断熱等級(1〜5等級)・ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)があります。
これらの基準に基づき、住宅や建物の断熱性能を評価してエネルギー効率を高める設計が進められています。
<haconiwa house 各種イベントに関してはこちら>

では、断熱性が低い家に起こる問題とはどのような事でしょうか?
以下のような問題が発生することが多く、快適性や住環境に大きな影響を与えます。
夏:外の暑さが室内に入り込みやすく、室内が暑くなりやすい。
冬:外の寒さが室内に侵入し、室内が冷え込みやすい。
結果として、冷暖房に頼らざるを得なくなる。
室温を一定に保つため、エアコンや暖房の稼働時間が長くなり、冷暖房費用が高くなる。
エネルギー効率が悪く、環境負荷が大きくなる。
外気温と室内温度の差が大きい場合、壁や窓に結露が発生。
結露が放置されると、カビやダニの発生、木材の劣化や腐食の原因になる。
室温が安定しないため、ヒートショック(温度差による体への負担)が起こりやすい。
冬場は冷え込む部屋が原因で、免疫力の低下や風邪を引きやすくなる可能性がある。
冬は「寒い」、夏は「暑い」と感じる時間が増え、居心地が悪くなる。
例えば、足元が寒いままの状態や、部屋ごとの温度差が激しくなる。
結露や湿気が原因で、断熱材や建材が劣化しやすくなる。
修繕費が増え、長期的にはコストがかさむ可能性がある。

断熱性能を高めるためには以下の方法が効果的です。
屋根、壁、床下に高性能な断熱材を導入する。
二重窓やトリプルガラスの採用、断熱フィルムの活用
気密性の向上:隙間を埋めるための施工や、気密シートの導入。
省エネ設備の導入:断熱性能が向上するエコ住宅設備を検討する。
断熱性の低い家は、初期費用が抑えられる場合がありますが、光熱費や修繕費が高くつく傾向があります。また、快適な生活を送る上で不満を抱える可能性が高くなるため、長期的には断熱性を高めることがコストパフォーマンスの良い選択となります。