
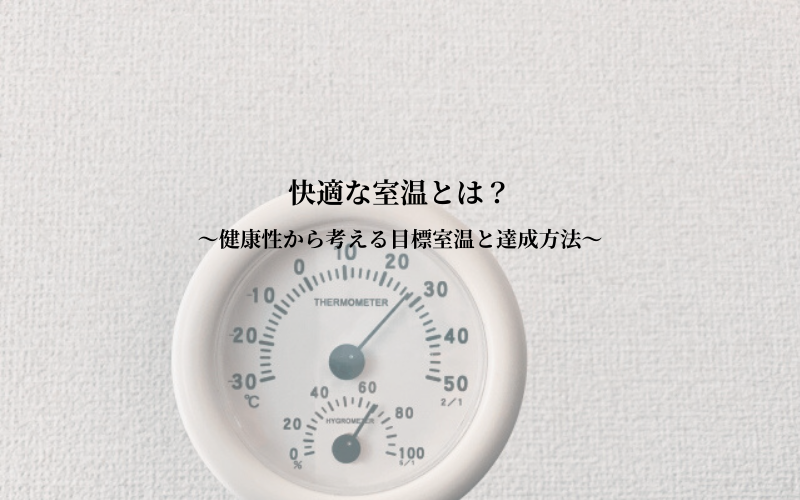
2025/3/3 COLUMN
快適な室温とは?
~健康性から考える目標室温と達成方法~
私たちが日々過ごす住宅の室温は、健康や生活の質に大きな影響を与えます。
寒すぎる室内は体調を崩す原因となり、暑すぎる環境は集中力を低下させることがあります。
快適な室温を維持することで、より心地よい暮らしを実現し、健康的な生活を送ることができます。
今回は、快適な室温の目標や達成方法について詳しくご紹介します。

快適な暮らしを実現するうえで住まいの「室温」は非常に重要な要素となります。
また、住まいの室温は健康と密接な関係があり、適温でない室温の住まいでは健康リスクが上昇することをご存じでしょうか。
住まいの室温が与える健康への影響をご紹介します。
寒い室温は血圧を上昇させ、特に高齢者にとっては心臓や脳血管疾患のリスクを高める可能性があります。
国土交通省の調査によると、室温が20℃から10℃に低下すると、高齢者の血圧が大きく上昇するというデータがあり、心疾患や脳梗塞等の発生リスクが上昇します。
室温が低いと、夜中に何度も目が覚めてしまい、睡眠の質が低下することがあります。
また、夜間頻尿になる場合もあります。
暖かい部屋から寒い部屋へ移動する際の急激な温度変化は、ヒートショックを引き起こす可能性があります。
家族が集まるリビングから浴室やトイレ、寝室へ移動した際に「寒い」と感じた経験があると思います。
特に、「リビング→脱衣室→浴室」への移動は、「リビング:室温(高)→脱衣室:室温(低)→浴室:室温(高)」となります。
暖かい空間の場合は血圧は血管が広がり、寒い空間になると血管は収縮します。
これにより、血管の急激な伸縮が起こりヒートショックの発生原因となってしまいます。
快適な室温は、ただ心地よいだけでなく、健康維持にも重要な役割を果たします。
寒暖差が激しいと体に負担がかかり、免疫力の低下や血圧の変動を引き起こす可能性があります。
そのため、健康を考えた適切な室温設定が必要です。
健康を維持するための目標室温は、季節や場所に応じて以下のように設定するとよいでしょう。
・冬季(居室):20℃前後
居室の気温はできる限り20℃あたりで維持することを目指しながら、およそ15℃以上になることを目指す。
厚生労働省や世界保健機関(WHO)によると、特に高齢者や子どもがいる家庭では 18℃以上 を推奨しています。
これより低いと、低体温症や血圧上昇のリスクが高まるため注意が必要です。
・冬季(非居室):居室の室温-5℃
居室から5℃まで低い室温になることを上限とし、常識的に考えると脱衣室は13℃以上にする。
居室と非居室の温度差を小さくすることが重要です。急激な温度変化はヒートショックの原因となります。
・夏季(暑い時期):27℃前後
居室の気温はできる限り27℃あたりで継続することを目指しながら、およそ32℃以下になることを目指します。
高温多湿な環境では、熱中症や脱水症状のリスクが高まります。
<haconiwa house 各種イベントに関してはこちら>

目標となる室温が決まってので、それを実現させる住まいのあり方を考えていきます。
そこで室温を規定する要素を挙げてみます。
●断熱性能(気密性能含む)
断熱性能とは、外気の影響を受けにくくし、室内の温度を一定に保つ性能のことです。高い断熱性能を持つ住宅は、冷暖房効率が良くなり、快適で健康的な住環境を維持しやすくなります。
壁・床・天井の断熱材を強化:断熱材の厚みを増やし、熱の移動を防ぐ。
高性能な窓(Low-Eガラス、二重・三重ガラス)を採用:冬の熱損失、夏の日射熱の侵入を防ぐ。
外皮(建物全体)の断熱性能を均等に:部分的に断熱が弱いと、温度ムラが生じる。
住宅の隙間を減らす(C値の改善):隙間風による温度変化を抑える。
適切な換気計画を行う:計画換気システムを導入し、熱ロスを防ぎつつ新鮮な空気を確保。
●蓄熱性能
蓄熱性能とは、熱を蓄えたり放出したりすることで、室内の温度変化を緩やかにし、快適な環境を維持する性能のことです。蓄熱性の高い建材を活用すると、暖房や冷房の効率が向上し、省エネルギーにもつながります。
冬場の昼間に暖まった熱を蓄え、夜に放出。
夏場は夜間の涼しさを蓄え、昼間に放熱。
●日射熱取得性能
日射熱取得性能とは、太陽の熱エネルギーを室内に取り込み、有効活用する性能のことです。適切に調整することで、冬は暖房負荷を減らし、夏は日射を遮ることで冷房効率を高めることができます。
冬は日射熱を活用:南向きの窓を大きくし、日中の太陽光で室内を暖める。
夏は日射を遮る:庇(ひさし)や軒、外付けブラインドで直射日光を防ぐ。
●通風性能
通風性能とは、自然の風を効率よく取り入れ、室内の空気を循環させる性能のことです。適切な通風設計により、換気が促進され、室内の温度調整や湿度管理がしやすくなり、快適で健康的な住環境を実現できます。
風の通り道を確保(対角線上に窓を配置)。
高窓や換気口を設け、上昇気流を利用(暖かい空気を排出し、涼しい空気を取り込む)。
室内扇風機やサーキュレーターで空気を循環(温度ムラを防ぐ)。
これらは「パッシブデザイン」と呼ばれる設計手法になります。
パッシブデザインとは自然のエネルギーを最大限活用し、室内を快適な空間とするための設計手法です。
しかし、本当のパッシブデザインは高度な技術と経験が必要になるため、「なんちゃってパッシブ」の住宅会社との違いを見極める必要があります。
●暖冷房範囲
●暖冷房時間
この中でも暖冷房要素の影響が大きいですが、単に暖房や冷房を使うだけでなく、湿度管理や換気、断熱対策などを組み合わせて、バランスの良い室温環境をつくることが大切です。
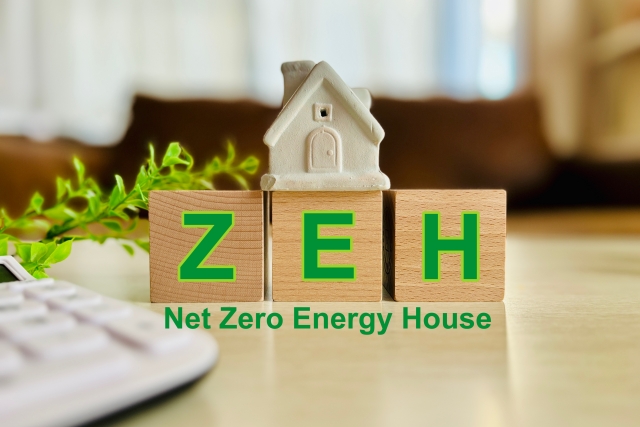
快適な室温を維持するためには、単に暖房・冷房に頼るのではなく、住宅性能(断熱・気密・通風・日射取得・蓄熱)を総合的に高めること が重要です。これにより、健康的でエネルギー効率の良い住環境を実現し、快適な暮らしが可能になります。